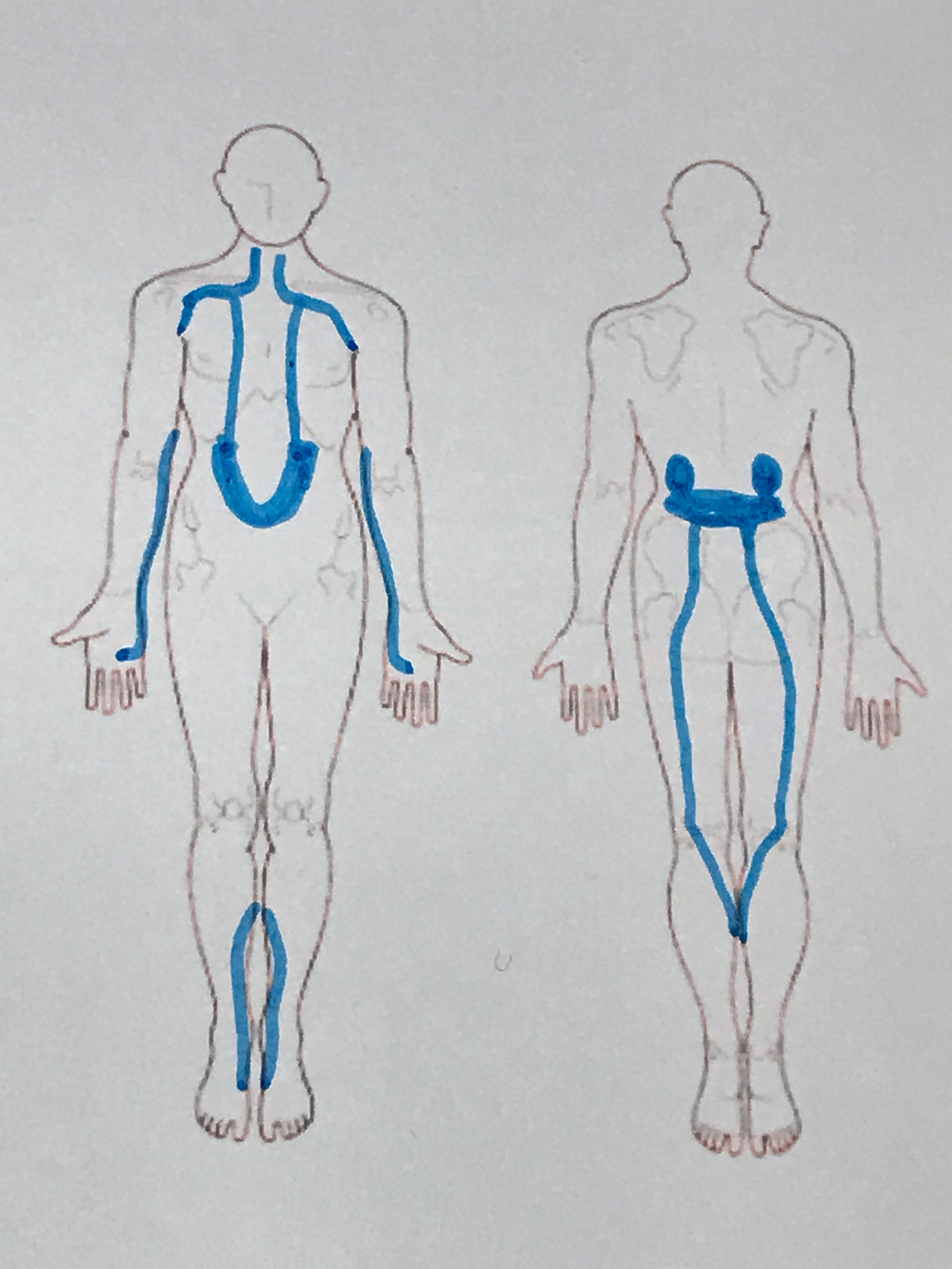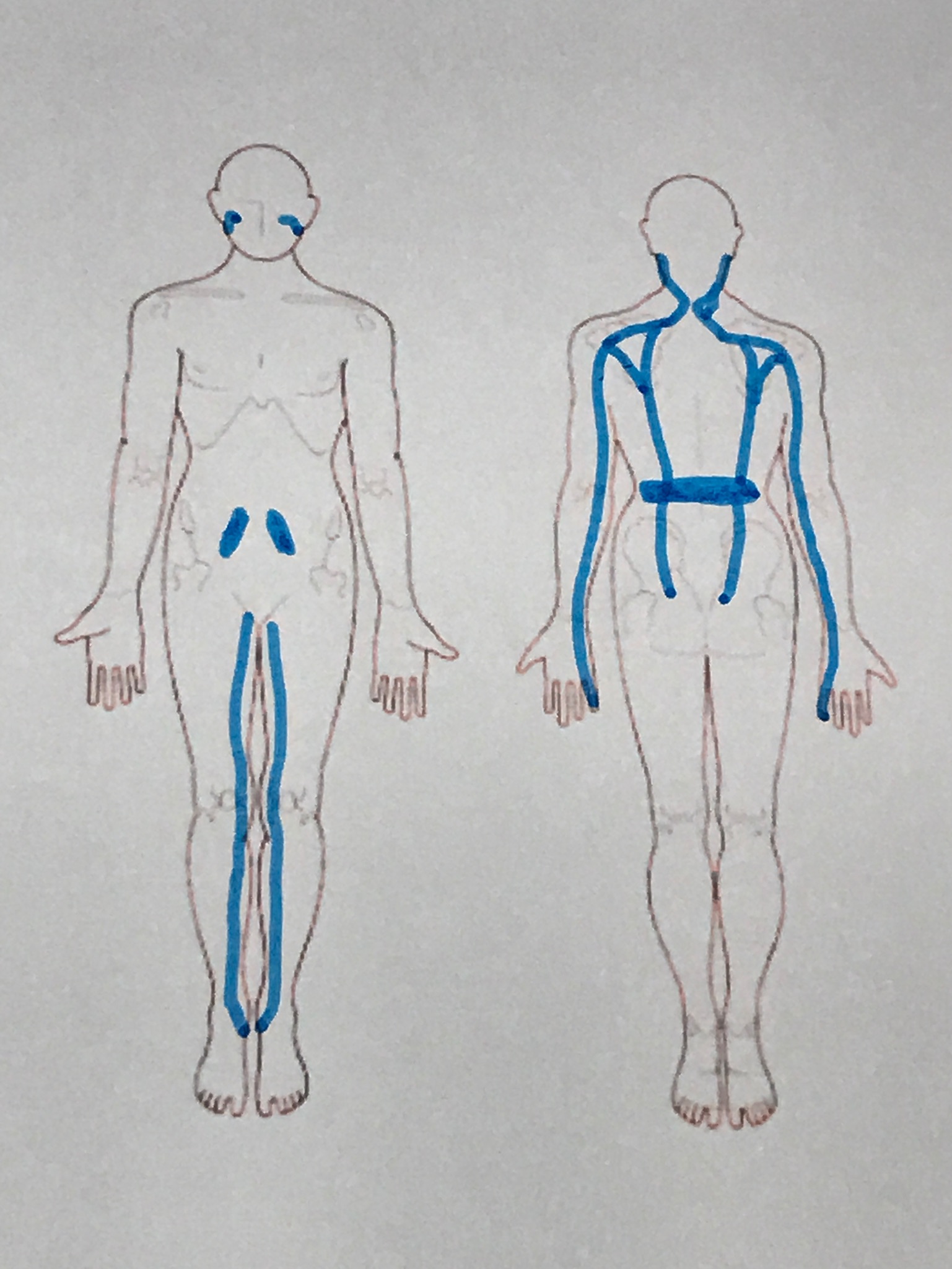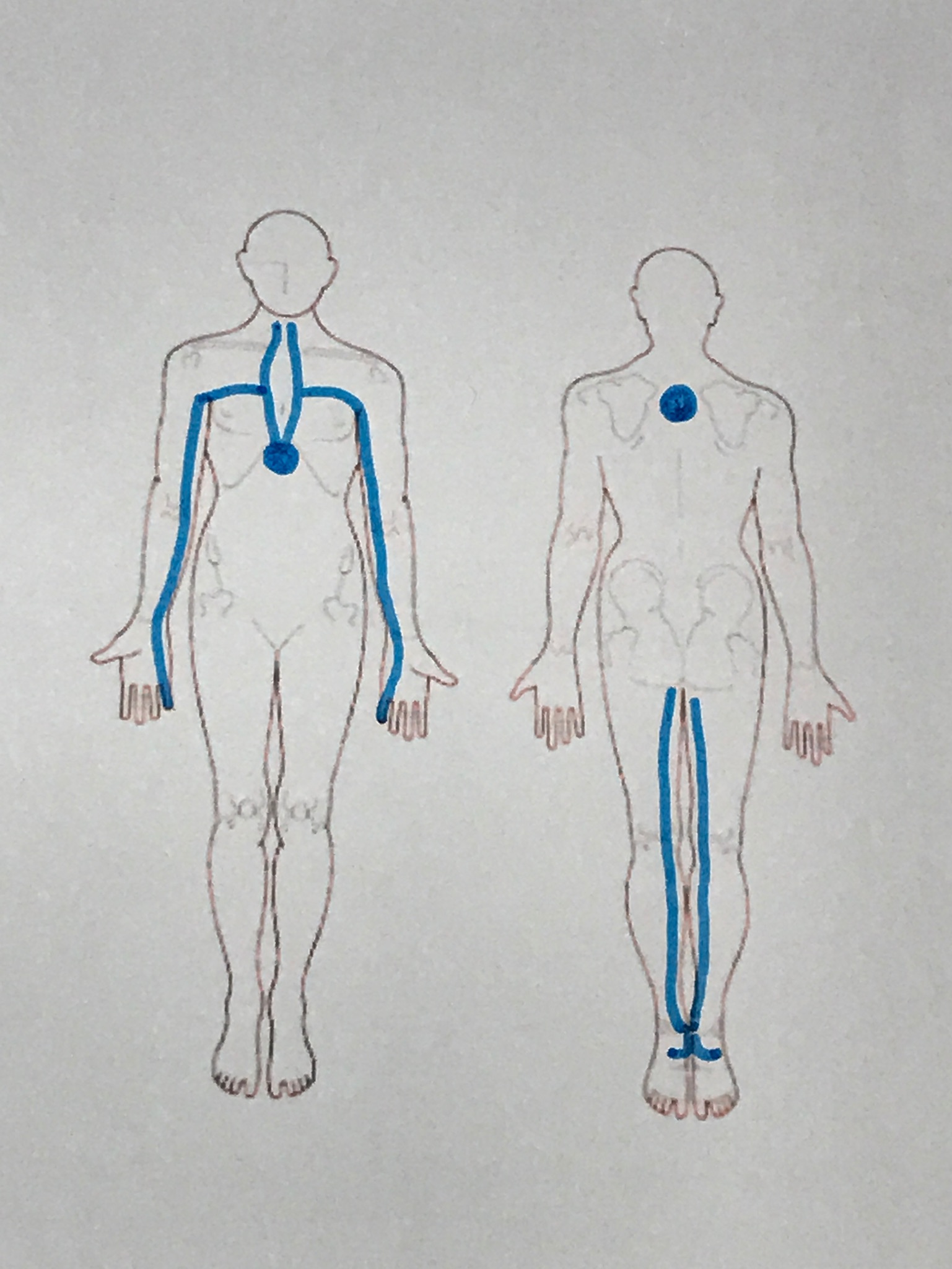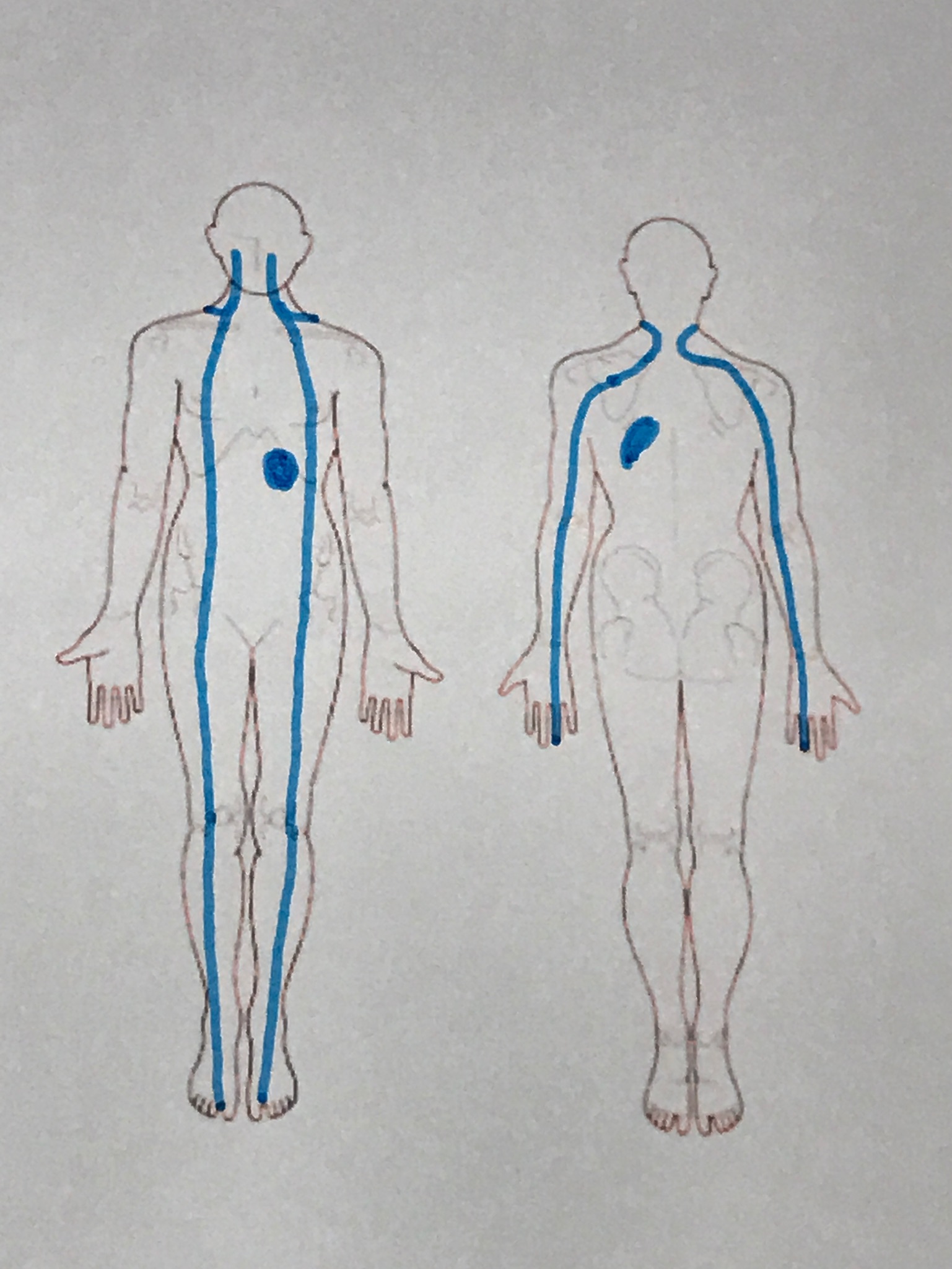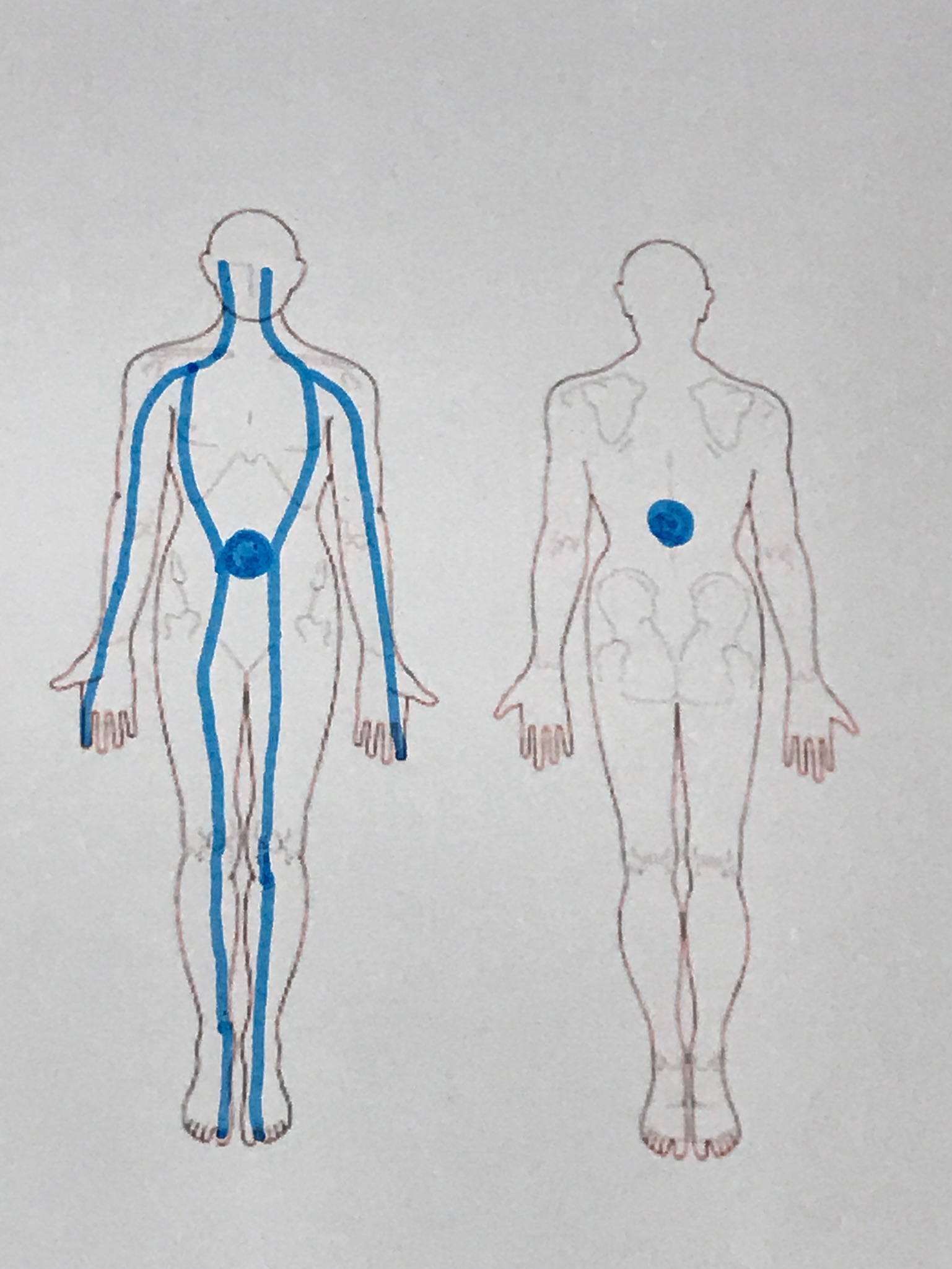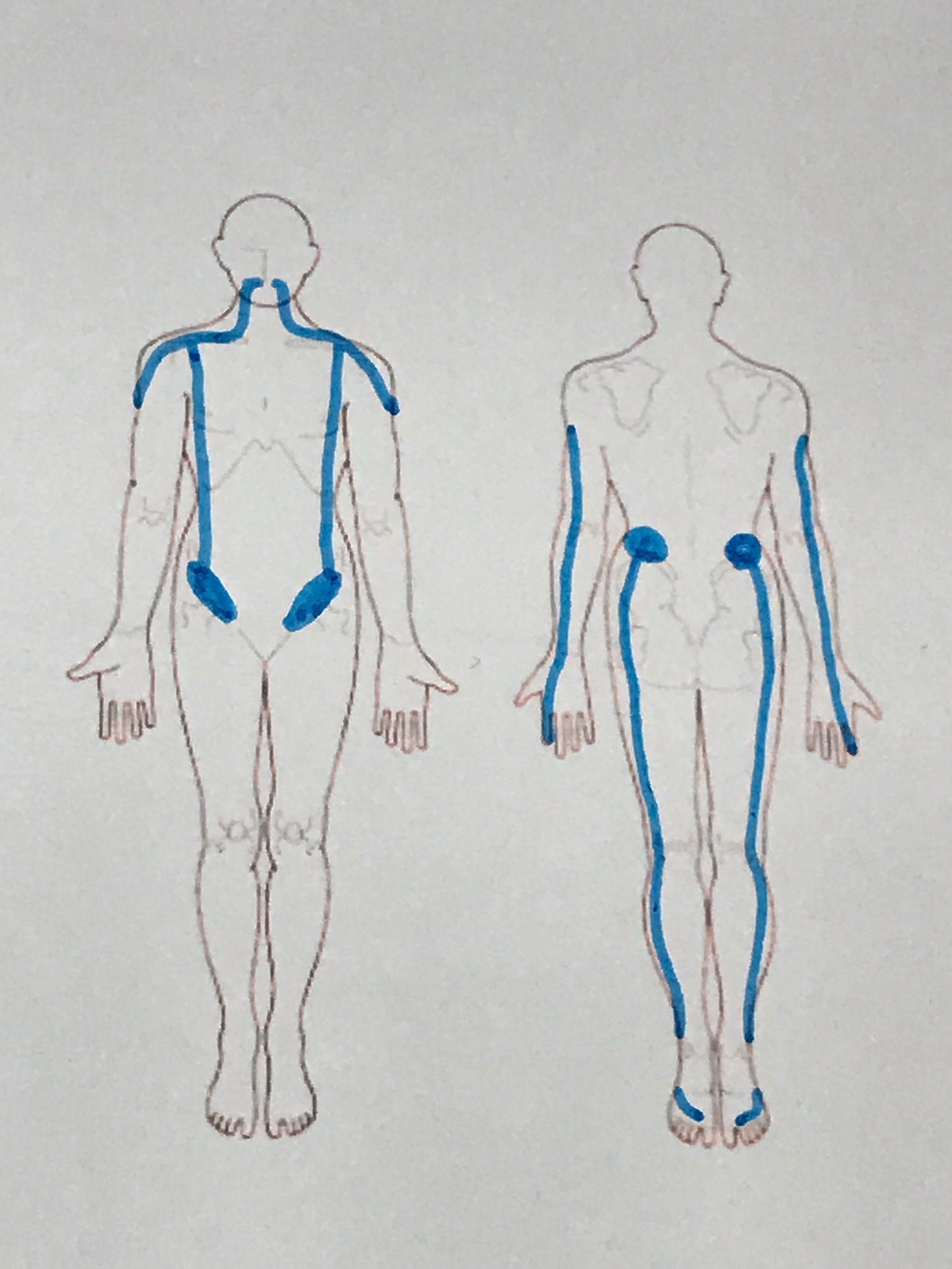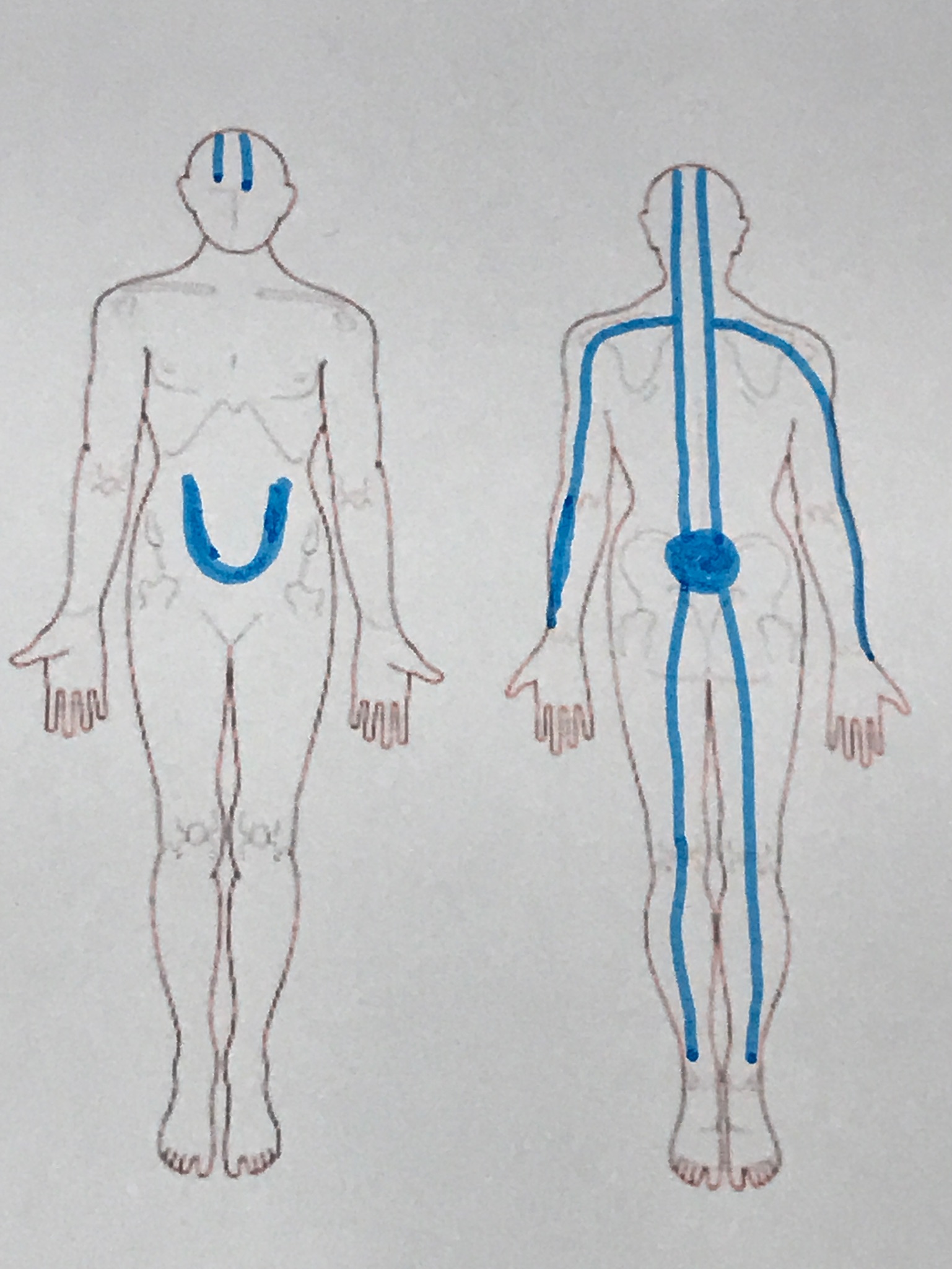
{膀胱経}
(働き)
・自律神経(脳下垂体)の働き ・尿の排泄
・生殖機能、泌尿器周辺の臓器を支配している。
(膀胱経が滞ると)
・神経緊張が強く物事に過敏に反応 ・背筋が突っ張る ・自律神経が弱る
・腰痛 ・目頭が重く、頭痛 ・下腹、足の冷え ・不眠、寝つきが悪い
・頻尿または、尿が少ない ・膀胱炎、残尿感 ・むくみ
(なぜ膀胱経が滞るのか)
・神経を使いすぎて気が休まらない(多忙) ・下半身の冷え
・人間関係のストレス ・時間や予定に追われる
(所属器官){腎経、膀胱経共通}
・腎臓 ・膀胱 ・歯 ・目の瞳 ・内分泌腺
・生殖器 ・自律神経 ・毛髪
(参考文献)増永静人著 1974「指圧」 医道の日本社 1975「スジとツボの健康法」潮文社
遠藤喨及 2011「タオ指圧、東洋医学の革命」ヒューマンワールド